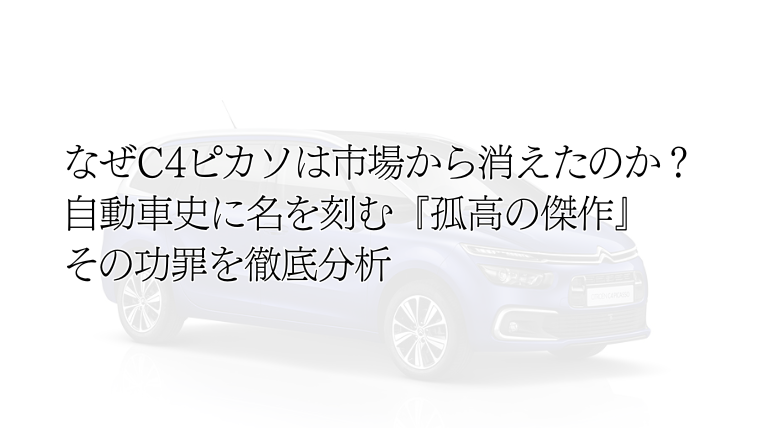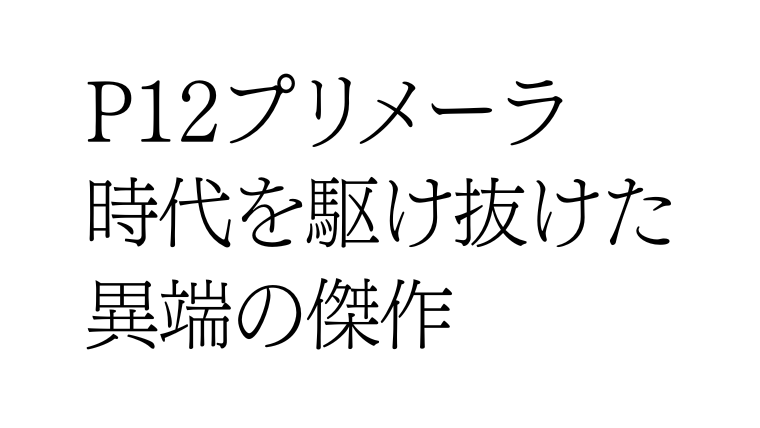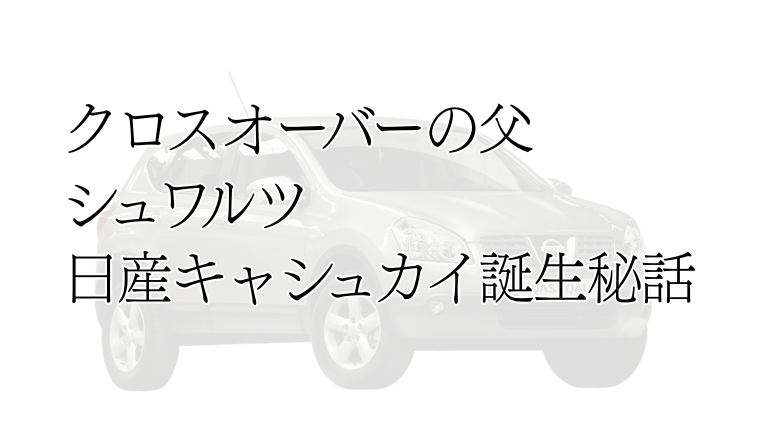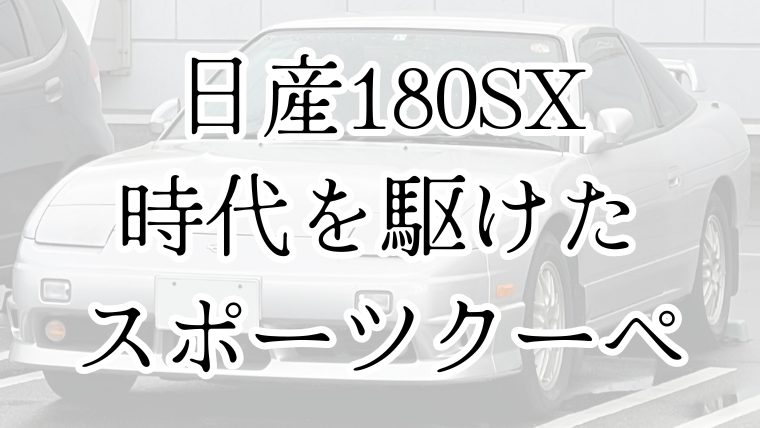時代が追いついた傑作、いすゞ・ピアッツァの真価
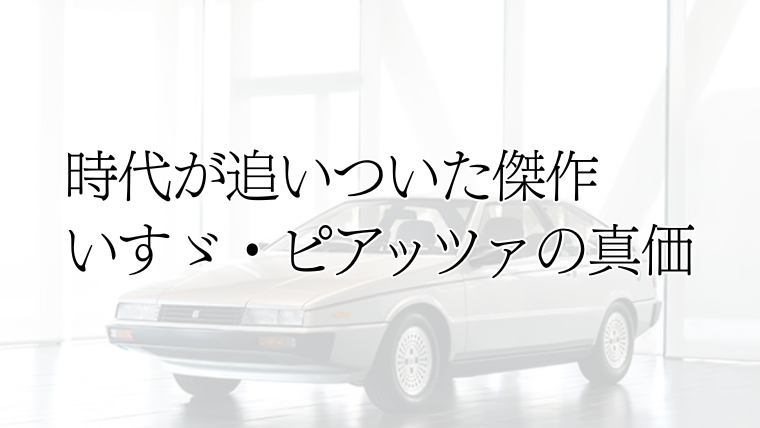
時代を先取りしすぎた悲劇の傑作か、それとも走る工業デザイン遺産か。今こそ知る、いすゞ・ピアッツァの真価

1981年、日本の自動車市場に一台のクーペが静かに、しかし鮮烈な衝撃をもって登場しました。その名は、いすゞ・ピアッツァ。イタリア語で「広場」を意味するこの車は、まさに人々が集い、語り合うべき芸術品でした。
自動車デザインの巨匠、ジョルジェット・ジウジアーロが描いた未来が、ほぼそのままの姿で公道を走り出したのです。しかし、その先進性は市場に完全には理解されず、商業的な成功とは裏腹に、ピアッツァは「悲運の傑作」として語られることも少なくありません。
あれから40年以上が経過し、ピアッツァはネオクラシックカーとして再び熱い視線を浴びています。
なぜ今、この車が再評価されているのか?そのデザインは自動車史に何を残したのか?この記事では、データとストーリーを交えながら、いすゞ・ピアッツァが持つ時代を超えた価値の核心に迫ります。
デザインの革命 – 公道を走るコンセプトカーの衝撃
「クラブのエース」の奇跡的な誕生

ピアッツァの物語は、1979年のジュネーブモーターショーに遡ります 1。そこでジウジアーロ率いるイタルデザインが発表したコンセプトカー「アッソ・ディ・フィオーリ(クラブのエース)」こそ、ピアッツァの原型でした 。
当時のデザインの主流が「折り紙細工」のような直線基調であったのに対し、アッソ・ディ・フィオーリは流れるような曲面でボディ全体を包み込み、来るべき80年代の空力デザイン時代を予見させるものでした。
そのデザインは、まさに革新の連続でした。
- 低いノーズとフラッシュサーフェス: 空気抵抗を極限まで減らすため、ボディとガラスの段差をなくした「フラッシュサーフェス」処理は、当時の量産車技術の常識を覆す挑戦でした。
- 未来的なコクピット: ステアリングから手を離さずに主要な操作ができるよう、スイッチ類をメーターの左右に集約した「サテライトスイッチ」は、まるで宇宙船の操縦席のようでした 。
通常、コンセプトカーが市販される際には、コストや技術的な制約からデザインの多くが変更されます。
しかし、いすゞの技術者たちは、ジウジアーロ自身が驚嘆するほどの忠実さで、この未来的なデザインを量産車「ピアッツァ」として世に送り出したのです。それはまさに「公道を走るコンセプトカー」の誕生でした。
ピアッツァのデザインがいかに異質で先進的であったか、同時代のライバルと比較することでより鮮明になります。例えば、人気を博したトヨタ・セリカXX(A60型)は、リトラクタブルヘッドライトを持つ点は共通していましたが、そのスタイリングはシャープなエッジが際立つ直線的なウェッジシェイプが基本でした 。これは70年代スーパーカーのデザイン言語を色濃く受け継いだもので、力強さを前面に押し出していました。一方、日産・シルビア(S110型)は、よりフォーマルなノッチバッククーペの様式に則り、平面的なパネル構成で落ち着いた佇まいを見せていました 。
これらに対し、ピアッツァは「ひとつの塊から削り出した」ような彫刻的で連続的な面構成を持ち、ヨーロッパの高級GTのような気品とエレガンスを漂わせていました。それは単に形が違うというだけでなく、自動車を工業製品としてだけでなく、芸術品として捉えるという、根本的なデザイン哲学の違いを物語っていたのです 。
唯一の妥協点は、当時の日本の法規がドアミラーを認めていなかったため、デザインの連続性を損なうフェンダーミラーを装着せざるを得なかったこと。
1983年にドアミラーが解禁された際、いすゞは「ピアッツァほどドアミラーの似合うクルマはない。」という広告コピーで、本来あるべき姿に戻った喜びを表現しました 。
市場のジレンマ – 美しすぎた故の苦悩
ライバルひしめくスペシャルティカー市場
1980年代初頭、日本の自動車市場は「スペシャルティカー」ブームの真っ只中にありました。強力なライバルたちが、市場の覇権を争っていました。
- トヨタ・ソアラ: デジタルメーターやマイコン制御オートエアコンなど、日本の技術の粋を集めた「ハイテク高級車」の王者。価格も200万円台後半からと、圧倒的なプレミアム性を誇りました 。
- 日産・レパード: ソアラに対抗する日産の豪華パーソナルクーペ。上質な内外装と6気筒エンジンで、真っ向から勝負を挑みました 。
- マツダ・コスモ: ロータリーエンジンという独自の心臓を持つ個性派。パフォーマンス志向の強いユーザーに支持されました。
- トヨタ・セリカXX: ソアラよりも若々しくスポーティなイメージで人気を博したGTカー。6気筒エンジンによる走りの良さが魅力でした。
この強豪たちに対し、いすゞはピアッツァの「デザイン」という一点で勝負を挑みました。ターゲットは、既存のヒエラルキーに縛られない、美意識の高い知的なユーザー層。しかし、この戦略には大きな課題が潜んでいました。
「見た目」と「中身」のギャップ
ピアッツァの最大のジレンマは、その未来的な外観と、ベースとなったシャシーがより大衆的な「ジェミニ」のものであった点にありました。
ソアラやレパードが上級セダンのプラットフォームから生まれる滑らかで余裕のある走りを提供したのに対し、ピアッツァの乗り味は、その革新的なスタイリングが抱かせる期待感には一歩及ばなかったのです。当時の自動車評論でも、エンジンの高回転域での騒音やライバルと比較した際の非力さが指摘され、「超一流の外観に、一流半のメカニズム」と評されることがありました。
いすゞはこの弱点を克服すべく、モデルライフの途中で矢継ぎ早に改良を施します。1984年には待望のターボモデルを追加。1985年には西ドイツのチューナーが監修したスポーティグレード「イルムシャー」を、そして1988年には英国の名門「ロータス」が足回りを引き締めた最上級グレード「ハンドリング・バイ・ロータス」を投入しました。
これらのモデルは専門家から高く評価され、ピアッツァの走りのポテンシャルを大きく引き出しました。しかし、市場に一度定着してしまった「デザインは良いが走りはそこそこ」という初期のイメージを完全に覆し、販売台数を劇的に回復させるまでには至らなかったのです。
現代における再評価 – なぜ今、ピアッツァなのか?
ネオクラシックカー市場の主役へ

発売から40年。かつて商業的に苦戦したピアッツァは、今、中古車市場で輝きを放っています。取引価格は高値で安定し、状態の良い個体は200万円を超えることも珍しくありません。例えば、最終型の希少グレード「ハンドリング・バイ・ロータス」が270万円で取引される一方、走行距離の少ない初期型「XG」も220万円の値が付くなど、年式以上に個体のコンディションや物語性が価格を左右する、典型的なコレクターズカー市場を形成しています 。
この価格高騰の背景には、いくつかの理由があります。
- ネオクラシックカーブーム: 80~90年代の日本車が、国内外で空前の人気となっています。当時憧れた世代が、今、その夢を叶えようとしているのです。
- 海外からの熱視線(25年ルール): 米国では製造から25年が経過した車は輸入規制が緩和されます。これにより、ピアッツァのようなユニークな日本車が海外コレクターの手に渡り、国内の希少価値がさらに高まっています。
- 時代を超えたデザイン価値: 時代が一巡し、ピアッツァの持つジウジアーロデザインの普遍的な美しさと先進性が、改めて「優れた工業デザイン作品」として評価されています。
困難さえも魅力に変える、オーナーたちの情熱
ピアッツァを維持し続けることは、決して容易ではありません。特に外装や内装、ピアッツァを象徴するサテライトスイッチなどの電子部品の多くはすでに生産が終了しています。しかし、この困難こそが、ピアッツァの価値を特別なものにしています。
- 熱心なオーナーコミュニティ: 「部品がなければ作る」を合言葉に、情報を交換し、助け合う。全国に存在するオーナーズクラブ「SOP (Slave of PIAZZA) TECHNICAL CLUSTER」は、「自分でいじる」をモットーに、ピアッツァを未来へつなぐための重要な拠点となっています 。彼らは自らを単なる所有者ではなく、この文化遺産を守る「学芸員(キュレーター)」だと考えているのです。
- 専門店の存在: 東京都羽村市には、いすゞ旧車の専門店「イスズスポーツ」が存在し、メンテナンスやレストア、時には部品製作の相談にも乗ってくれる、オーナーにとって心強い味方となっています。
この「維持の困難さ」と、それを乗り越えようとする「人々の情熱」。この二つが組み合わさることで、ピアッツァは単なる古い車ではなく、生きた文化遺産として存在し続けているのです。
結論:ピアッツァが自動車史に残した、色褪せないレガシー
いすゞ・ピアッツァは、販売台数という物差しだけでは測れない、大きな遺産を私たちに残しました。それは「コンセプトカーの夢を、量産車という現実の世界に解き放った」という、いすゞの情熱そのものです。
かつての弱みであった「ニッチな存在感」は、時を経て「希少性」という強みになりました。先進的すぎたデザインは、「時代を超越した魅力」として再評価されています。
ピアッツァの物語は、自動車メーカーがいかに先進的なデザインと市場の需要のバランスを取るべきかという教訓を私たちに与えてくれます。
そして何より、一台の車が、これほどまでに人の心を動かし、情熱をかき立て、コミュニティを育むことができるという事実を教えてくれます。
もしあなたが街でこの流麗なクーペを見かけることがあれば、思い出してください。それは単なるクラシックカーではありません。デザイナーの魂と、技術者の執念、そしてオーナーたちの愛情によって走り続ける、「走る工業デザイン遺産」なのです。